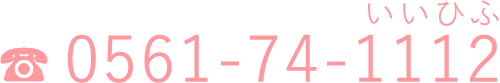とびひDermatology
とびひDermatology
とびひとは

とびひ(伝染性膿痂疹)は、主に細菌感染によって発症する皮膚疾患の一種です。
特に子どもに多く見られますが、大人も感染することがあります。とびひの原因菌は主に「黄色ブドウ球菌」や「溶血性連鎖球菌(A群β溶血性連鎖球菌)」で、皮膚にできた傷や虫刺されなどの小さな傷口から細菌が侵入し、増殖することで発症します。
とびひには大きく分けて「水疱性膿痂疹」と「痂皮性膿痂疹」の2種類があります。
- 水疱性膿痂疹:水ぶくれ(水疱)ができ、それが破れると周囲へと感染が広がるタイプ。
- 痂皮性膿痂疹:かさぶた(痂皮)ができ、炎症が強く、腫れや発熱を伴うこともあるタイプ。
子どもがかきむしる前に!「とびひ」は早めの治療が重要
とびひは、非常に感染力が強く、患部をかきむしることで他の部位や周囲の人へと感染が広がります。そのため、早期発見と適切な治療が重要です。特に子どもは、かゆみを我慢できずに患部をかきむしってしまうため、症状が急速に悪化することがあります。
とびひの治療法
- 外用薬の使用
- 症状が軽度の場合や局所的な感染に対しては、抗菌薬の入った外用薬を使用します。これらは感染を引き起こす細菌を直接的に退治する効果があります。
- 内服薬の併用
- 症状が広がっている場合や重度の場合、外用薬に加えて抗生剤の内服が推奨されます。
- かゆみのコントロール
- とびひによるかゆみが強い場合、抗ヒスタミン薬やステロイド外用薬が併用されることがあります。これにより、かゆみや炎症を軽減することができます。
とびひは感染防止のために患部を清潔にすることが重要です。ぬるま湯と石鹸を使って患部をやさしく洗うことやガーゼで保護することが有効です。
とびひは大人も感染する?正しいケアと予防法
とびひは子どもに多い病気ですが、大人も感染する可能性があります。特に免疫力が低下している人や、皮膚に傷がある人は感染リスクが高くなります。
大人のとびひの特徴としては、患部の炎症が強く、痛みや腫れが出やすいです。過度のストレスや不規則な生活が発症リスクを高めるとされています。
予防のポイント
- 手洗いの徹底:とびひの原因菌は手を介して広がるため、こまめな手洗いが重要。
- 傷口の適切なケア:小さな傷でも放置せず清潔に保つ。
- 共有物の管理:タオルや衣類を共用しない。
とびひは特に夏に流行しやすい病気です。日本の夏は高温多湿であり、細菌が繁殖しやすい環境が整っているため、感染が広がりやすくなります。特にプールや水遊びの後は、皮膚がふやけて傷ができやすく、とびひに感染しやすい状態になります。 家族にとびひの症状が出た場合には、家族内での感染を防ぐため、個別のタオルや枕カバーを使用することや高温での洗濯・乾燥を心がけることが重要です。
厚生労働省の感染症情報によると、とびひの発症率は6月〜9月にかけて最も高くなる傾向があります。この時期は特に注意が必要です。
「ただの虫刺され」と油断しないで!とびひの見分け方と治療法
とびひは初期症状が虫刺されやあせもに似ているため、見分けがつきにくいことがあります。しかし、症状の進行が速く、適切な治療を行わないと感染が広がるため、早めの判断が必要です。
とびひと虫刺されの違い
| 特徴 | 虫刺され | とびひ |
|---|---|---|
| かゆみ | 強い | かゆみがあるが、痛みも伴うことがある |
| 形状 | 赤く腫れる | 水疱や膿ができ、破れて拡がる |
| 進行速度 | ゆっくり | 急速に拡大 |
| 感染性 | なし | あり(他の部位や他人に広がる) |
とびひは放置すると重症化し、まれに蜂窩織炎(ほうかしきえん)や敗血症といった合併症を引き起こす可能性があります。そのため、「ただの虫刺され」と油断せず、早めに皮膚科を受診することが大切です。
当院では、とびひの診断と治療に力を入れております。迅速な診察と適切な治療で、患者様の早期回復をサポートいたします。とびひの症状にお悩みの方は、愛知県日進市のたけのやま皮ふ科までご相談ください。